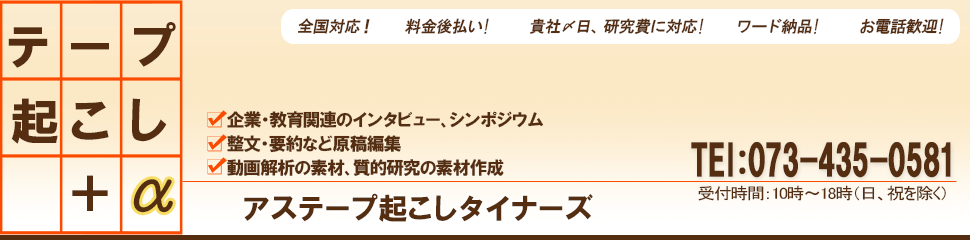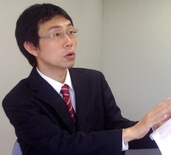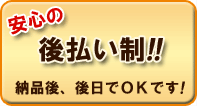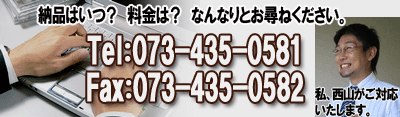笑い声は文章化すべきでしょうか?
答えとしては、
- 原稿の作成の仕方による
- 文脈による
です。
原稿の作成の仕方による
ケバ取りテープ起こしや、整文・要約などの場合は、原則、文章化は不要です。いっぽうで、そのままテープ起こしの場合は、必要とまでは言い切れませんが、あったほうが望ましいです。
なお、文章化する場合は、「あはははは」など笑い声の音を記号化するも良し、(鈴木さん笑う)などの状況説明でもいいでしょう。音を記号化は、たとえば「あはははは」の「は」の数までこだわらなくてもOKです。
ただし、(苦笑)や(失笑)(爆笑)など、笑い方の強弱・種類を表す表現はしないほうが賢明です。
これらはその音声を聞いた人(つまり、あなた)の恣意的な判断であり、実際に苦笑や失笑・爆笑であるかは確証が持てないためです。
文脈による
上記で、「ケバ取りテープ起こしや、整文・要約などの場合は、原則、文章化は不要です」とお伝えしました。
では、例外とは何かと言えば、文脈判断です。
文脈的に、笑い声がないと前後が繋がらない箇所があれば、その場合は笑い声を記載すべきです。このことで前後が繋がり、読み手が理解することができます。
つまり、このあたりは機械的に要不要を決められるものではなく、文脈理解が必要であり、文脈を理解するためには何の話をしているかの理解が必要になりますので、読み取ることに重心を置くとおのずと判断しやすくなるのではないかと思います。