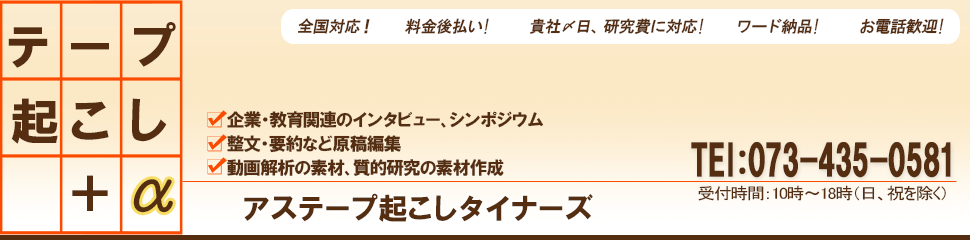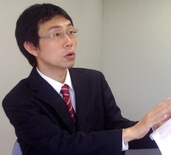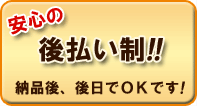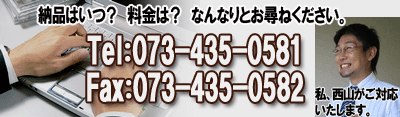講演会の要約を行う際の基本的な手順と考え方を、一般の方向けに解説します。
「いきなり要約」は失敗のもと
講演の録音を聞きながら、「ここは重要だからメモして、ここは省いて…」と同時進行で要約しようとしていませんか?
実は、これが最も難しい方法なのです。
音声を聞きながら内容を理解し、同時に重要度を判断して、さらに文章として書き起こす。この3つの作業を同時に行うのは、プロでも非常に負荷が高い作業です。
正しい手順は「テープ起こし」→「要約」の2段階
効率的に、そして質の高い要約を作るための基本は:
ステップ1: まず丁寧にテープ起こし(文字起こし)を行う
ステップ2: 完成した文字原稿を基に要約作業を進める
この2段階のアプローチが、確実で質の高い成果につながります。
要約の成否を決める「内容理解」の重要性
さて、テープ起こしが完了したら、すぐに要約作業に入りたくなるかもしれません。
しかし、ここでもう一つ重要なステップがあります。それが講演内容の徹底的な理解です。
内容理解のためにやるべきこと
1. 講演の音声を改めて聞き直す
文字だけでは伝わらないニュアンスや強調点を確認
2. ケバ取り原稿をじっくり読む
(ケバ取り=「えー」「あのー」などの不要な言葉を整理したもの)
全体の流れと論理構成を把握
3. 配布資料や参考資料に目を通す
講演者が伝えたかった背景や補足情報を理解
この3つをしっかり行うことで、講演の全体像が明確になります。
実は、この段階までくれば要約作業の3割は完了していると言っても過言ではありません。それほど内容理解は重要なのです。
ここで多くの方が誤解しているポイントがあります。 要約とは、「長い文章から言葉を減らしていくパズル」ではありません。 要約とは、講演録を基にして新たに原稿を構成し直す作業です。 つまり: これが本来の要約作業なのです。 内容を十分に理解したら、いよいよ実際の要約作業に入ります。 ここで意識すべき3つのポイントをご紹介します。 講演のすべてを残すことはできません。 このような視点で、残すべき部分と省くべき部分を見極める判断力が求められます。 講演は「話し言葉」ですが、要約文は読まれることを前提とした「書き言葉」である必要があります。 読み手がスムーズに理解できる文体に整えることが大切です。 最も重要なのは、講演者の意図を損なわないこと。 短くすることに気を取られて、本来の意味やニュアンスが変わってしまっては本末転倒です。 これらを常に意識しながら、的確に再表現することが求められます。 ここまで読んで、「やっぱり要約は専門的な技術が必要なんだな」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。 その通りです。だからこそ、私たち原稿作成のプロフェッショナルが存在しています。 そんなときは、ぜひ専門家の力を借りることも検討してみてください。 私たちは日々、さまざまな講演・セミナー・会議の要約を手がけています。内容の理解から文章の再構成まで、確かな技術でサポートいたします。 お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。 講演会の要約でお悩みの方、まずは一度お声がけいただければ幸いです。 ケバ取りテープ起こし→要約はこちら
「要約=文字数削減」ではない!本質を理解する
要約の本質は「原稿の再構成」
– 単に文を短くするのではなく
– 講演の趣旨・構成・流れを深く理解した上で
– 重要な要素を抽出し
– 読みやすい形に再構築する実践!要約作業の3つのポイント
ポイント1: 重要度の選定
ポイント2: 話し言葉から書き言葉へ
ポイント3: 意味とニュアンスの保持
「プロに任せる」という選択肢も
https://www.tapeokoshi.net/about-youyaku/