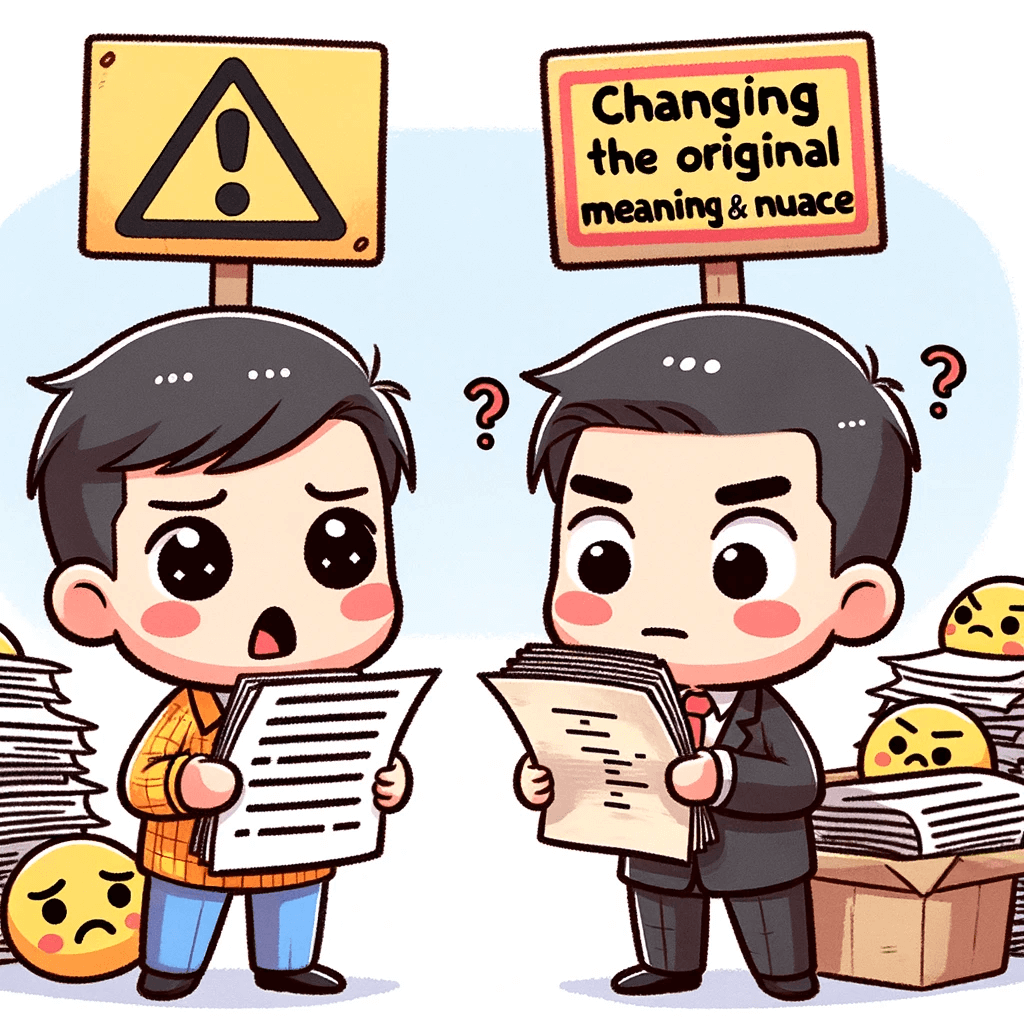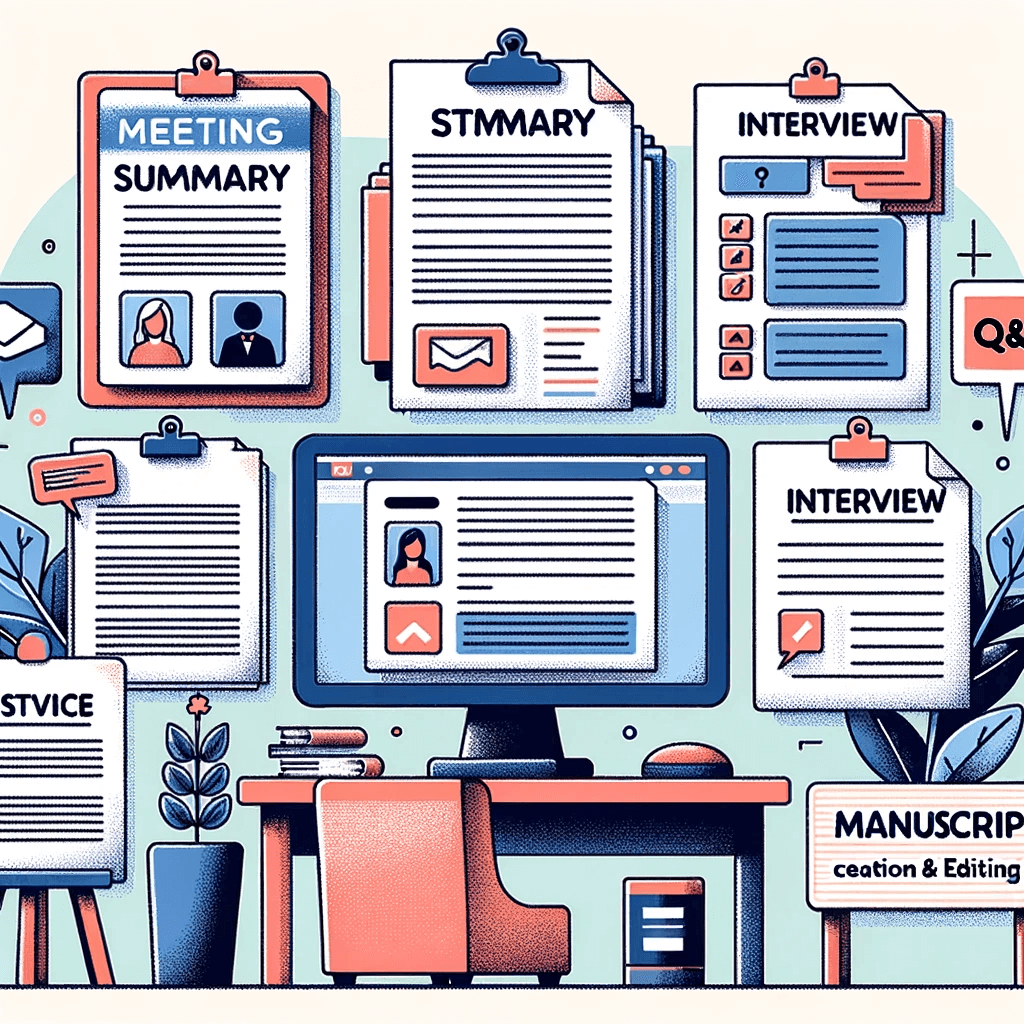整文はテープ起こしの文章化の仕方の一つです。
原稿作成の要素が入ることから、弊社が得意とする作成の仕方です。
この整文、どちらかと言えば、原稿作成を提供する側(弊社)の言葉のようであり、この字面からは「文章を整えてくれるんだなあ」ということは分かりますが、しかし、お客様から見れば、どのように文章化してくれるのか明確になりづらいと思います。
じつはかなり便利な文章化の仕方ですので、ここで少しかみ砕いてご説明したいと思います。
文字起こしにかかわず、整文とは?
一般に「整文」とは、文章をより適切で、読みやすく、そして伝わりやすい形に修正・編集することを指します。
具体的には以下のようなことを行います。
1. 文法・語彙の修正:誤った文法や適切でない言葉を正確なものに修正します。
2. 文語体に修正:口語体から文語体に修正する。
3. 情報の整理:文章内の情報を論理的な順序に整理し、流れを明確にします。
4. 冗長な表現の削除:重複している情報や不要な表現を取り除き、文章をコンパクトにします。
5. 構造の修正:長すぎる文を分割したり、短すぎる文を結合するなどします。
6. 明瞭化:曖昧な表現や不明確な部分を具体的にし、明確に伝えるための修正を行います。
定義づけは機関・団体によって若干の違いはあるでしょうが、おおむね、これらが全般的な(ジェネラルな)意味での整文です。
文字起こしにおける整文
いっぽうで、「文字起こしにおける」という冠が付くと、少し変わってきます。
上記の1については、変更はありません。このとおりです。
2についても変更はありませんが、ニュアンスが変化する可能性があるため、気を付けなければなりません。
3については、注意が必要になります。
「文章内の情報を論理的な順序に整理し、流れを明確に」するのは良いのですが、どなたかの発言内容の議事録である文字起こしの原稿にこれを反映すると、非常に高い確率で発言のニュアンスが変わり、また、気を付けないと意味自体が変わってしまいます。
整えることで流れが明確になるのは良いことなのですが、どうしても整える強度を強めてしまうと、元のニュアンスや意味が変形してしまう可能性があるため、注意が必要です。
4~6もこれに近いことが言えます。
4「重複している情報や不要な表現を取り除き、文章をコンパクトに」することでニュアンスや意味が変わることは、まずありませんが、重複しているのは話し手の(何度も同じ話をするという)話し方に依っているのか、それとも大切なことなので同じことを複数回話したのかで、理解は変わってきます。もし前者であれば取り除いてコンパクトにすべきでしょうし、後者であれば、残しておくことに意義があります。
5「長すぎる文を分割したり、短すぎる文を結合するなど」することで意味が変わることはありませんが、発言のニュアンスが変わる可能性があるため、注意が必要です。
6「曖昧な表現や不明確な部分を具体的にし、明確に伝えるための修正を行」う場合、本当に曖昧で不明確であるのか、あるいは発言者が曖昧で不明確な話し方を意図しているのかで、理解は変わってきます。もし前者であれば修正すべきでしょうし、後者であれば、そのままであることに意義があります。
総じて、整文の目的は、文章がその対象とする読者にとって理解しやすく、そしてその内容が正確に伝わるようにすることです。あくまで文章を「整える」ことの範囲内でのみ原稿に手を入れるべきであり、「整える」の意味を拡大解釈して創造(creation)という意味での「修正」「編集」をしてしまうとそれは整文ではなくなってしまいますので、注意が必要です。
整文 文字起こしはこちら
https://www.tapeokoshi.net/seibun.html